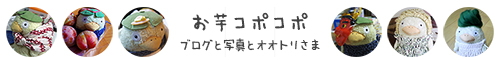カケルは学校帰りに公園に寄った。
『寄り道はいけません。ランドセルを家に置いてから、遊びにでかけましょう。』と、学校では言われている。けれど、何となく家に帰りたくなかった。ランドセルを茂みの中に隠し、ブランコを漕ぐ。
今朝、お母さんとケンカをしてしまったのだ。いつもなら急いで家に帰ってオヤツを食べてから遊びに出かけるけれど、今日はお母さん、きっと怒っているだろうからオヤツも無いだろう。『でも、僕は悪くない』と、カケルは思っていた。
朝、僕だって忙しいのにお母さんが「庭のお花に水をやって」とか言うんだもん。そんなことしてる時間無いよって言ったら、教科書の準備を前の日にしておかないからよって怒られたんだ。別にその日の朝に準備したっていいじゃないか。お花に水をやるのは僕の仕事じゃないもん…。
ブランコを漕ぎながら、カケルはそんな事をぐるぐると考えていた。家に帰ったらまたお母さんと言いあいになるんじゃないだろうか。そう思うとなかなかブランコから降りられないのだった。
この公園はとても小さな公園で、遊具もブランコと滑り台しかなくて、いくつかのベンチと小さな砂場と水飲み場、あとは花壇があるぐらい。すぐ近くに、もっと大きな公園があって、ほとんどの子供たちは大きな公園に遊びに行く。アスレチックジムもあるし、ジャングルジムやシーソーもある。だから、この小さな公園にはカケルしか居なかった。もう30分くらいずっとブランコを漕いでいるけど、誰も来ない。
さすがにそろそろ帰ろうかな、と思った時だった。ブランコから降りて周りを見渡すと、花壇にしゃがみこんでいるおじさんが居るのに気がついた。来た時は気付かなかった。何をしているんだろう。
カケルは茂みに隠したランドセルを背負うと、花壇の方に歩み寄ってみた。おじさんは花壇の花に顔を近づけるようにして、じっと動かないでいる。かと思うと少し横にずれて、また花に顔を近づける。花に顔を近づけているというよりは、顔を横に向け、耳を花に近付けているみたいだ。
「あの・・・何してるんですか?」
カケルが思い切って声をかけるとおじさんはくるりとコチラを向いた。
「おお。少年。変なおじさんが居るって思われちゃったかな。」
「いえ・・・何してるのかなって思って。」
「花の声を聞いてるんだ。」
「花の声?花がしゃべるんですか?」
「うん。そうだよ。」
「うそだー!」
そう言いながらも、カケルはおじさんの隣にしゃがみ、おじさんと同じように花に耳を近づけてみた。
「なんにも聞こえないよ!」
「そうかあー。おじさんには聞こえるんだけどなあ。お水が欲しいよーとか、もうすぐ雨降るよーとか、チョウチョの家族が旅行に来たよーとか、いろいろ。」
カケルは、もう一度花に耳を近づけてみる。
「やっぱり、何にも聞こえない!おじさん、嘘ついてるんでしょ。」
「嘘なんかついてないよぉ。おじさんには特別な能力があるのかもしれないねえ。」
「ふーん。」
ちょっとつまらなそうな顔をしてカケルは立ち上がり、足元の小石を蹴った。
しばらくして、おじさんも立ち上がった。手のひらと膝についた土をぱたぱたと払う。なんとなく二人は、花壇のすぐそばのベンチに座った。
「少年、名前何て言うの?」
「カケル。」
「カケルくんかあ。おじさんは植木って言うんだよ。」
「うえき?植木鉢のうえき?」
「うん。まあ、そうだなあ。植木等のうえきなんだけどなあ。」
「うえきひとし?」
「まあいいや。植木って言うんだ。」
「うえきおじさん。」
「そうそう。うえきおじさんって言うんだ。あとね、あの花は、パンジーって言うんだよ。パンジーさん。」
「ぱん爺さん?」
「ははは。お爺さんではないかなあ。」
「おじさん、いつもここで花の声聞いてるの?」
「いや。いつも色んなところの花の声聞くんだよ。ここは初めて来た。小さいけど、いい公園だね。ちゃんと花の手入れがされてて。」
「花なんかどうでもいいもん。遊ぶとこ少ないから向こうの公園の方がいい。」
カケルはそう言って大きな公園がある方を指差す。
「どうでもいいってこたないだろう。綺麗だろう、お花。」
「どうでもいいもん。女みたいだもん。花なんか見てんの。」
「女みたいかあ。おじさんも、女みたい?」
「全然女みたいじゃない。」
「じゃあいいじゃないかー。花見てたって女になりゃしねえよお。」
「ふーん。」
またつまらなそうな声を出すカケル。でも何だかおじさんと喋っているのは、楽しかった。
「カケルくん、なんでランドセルしょったまま公園に居るの?」
「お母さんとケンカした。」
「ほーう。家帰りたくないんだ?」
「うん。でもおなか空いたし、もう帰る。」
「なんでケンカしたの?」
「朝お母さんが庭の花に水やっといてとか言って、僕学校の準備で忙しいからそんな暇ないって言ったら、お母さんが怒って学校の準備は寝る前にしなさいとか言うから。」
「そうかあー。それはカケルくんもちょっと悪いなあ。」
「なんで。」
「お母さんのお手伝い、しないといけないよぉ。」
「だって庭のお花はお母さんのだもん。僕関係ないもん。」
「カケルくんは毎日お母さんのごはん食べてるんだろう?」
「うん。」
「でもレストランとかに行ったらお母さんのごはんじゃないのも食べるだろう?」
「うん。食べる。」
「お花だっていつもお母さんからお水もらってるけど、カケルくんがお水あげたっていいんだよぉ。」
「なにそれ。」
「カケルくんは、レストランなの。コックさん。」
「コックさん?」
「そうそう。料理をしないコックさん。植木鉢はお水もらったら元気に頑張れるんだよ。カケルくんだってごはん食べたら元気に頑張れるでしょ。」
「うん…」
「じゃ、お母さんのお手伝いで植木鉢にお水あげられるね?」
「んーーー。」
カケルは納得のいかない表情だ。
「それじゃあね。約束だよ。お母さんと仲直りするんだよ。いつかおじさんみたいにお花の声聞こえるようになるかもしれないよ。」
そう言っておじさんはカケルの家とは反対の方向へ歩いて行ってしまった。カケルはしばらくおじさんの背中を見ていたが、くるりと方向を変え、家に向かって歩き始めた。
「ただいまー」
「おかえり。遅かったわね。」
「うん。ちょっと寄り道してた。お母さん。朝、ごめんなさい。」
「私も怒ってごめんね。ねえ、カケル、見て。お花咲いたよ。」
お母さんは庭を指差した。
「あ。パンジーさんだ。」
「あら。あんたパンジーって知ってるの?」
「さっき公園でおじさんに教えてもらったのと同じ花だもん。」
「おじさんって?」
「うえきおじさんって言うの。花の声聞いてる人なの。」
「花の声?」
カケルはランドセルを下ろし、サンダルをひっかけて庭に出た。
「こうやって、花に耳を近づけて聞くの。僕は聞こえないって言ったんだけど、そのおじさんは花の声が聞こえるんだって。」
「へーえ。私もやってみようかしら。」
「何も聞こえないと思うよ。」
「あら。聞こえるわよ。カケル、早く宿題やんなさいって言ってる。」
「嘘だ。」
「ほんとよー。ふふふ。」
お母さんは、とっても嬉しい気持ちでいっぱいだった。朝、自分がちょっとイライラしていたせいでカケルとケンカしてしまって、何て謝ろうかとパートに出ている間、ずっと考えていた。でも、なんだか不思議と、自然に、仲直りができてしまった。
次の日から、カケルは自分から進んで庭にお水を撒くようになった。時々、忘れてしまうこともあるけれど。そして、花が咲くたびにお花に耳を近づけてみた。
お花が、『ありがとう』って言った…わけないか。あのおじさんも、お母さんも嘘ついてるだけだもん。お花は喋らないもん。
そんな風に思いつつも、やっぱり時々、お花に耳を傾けてしまうカケルなのだった。