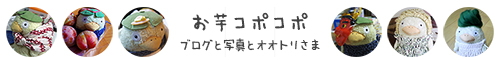この世には、ほっぺた拾いオバケ、というやつが居るそうだ。目には見えないが、評判の良い飲食店には、大抵必ず住み着いているらしい。お客さんがあまりに美味しいものを食べ、ウッカリ落としてしまったほっぺたを拾い歩いているオバケだ。
もともとは美食家として生きていた人々の魂が化けたものだと言われている。まあるくてかわいい姿をしているらしい。(・・・まぁ、目には見えないんだけど。雰囲気的に。)
この世に美味しいものがある限り、存在し続けるおばけなのである。
そのオバケたちは、落っこちたほっぺたを拾い上げると、品定めするように数秒間見つめ、そして箱の中にそっとしまうらしい。落ちているほっぺたは、ピンポン玉サイズぐらい。オバケたちが持っている箱の中には仕切りがあって、1箱に十数個ぐらいのほっぺたが収められるようになっているらしい。
以上のことは、僕が図書館で調べた基本情報である。目に見えないはずのオバケなのに、どうしてこんな生態レポートが書けるのか謎だけど、世界のオバケ百科、みたいな本に書いてあった。誰かがでっちあげたデタラメかもしれないけれど、僕はこのオバケに強く興味を惹かれ、とりつかれたかのように調べまくった。
調べまくった結果、色んなことがわかったけれど、オバケによって拾われたほっぺたが、その後どうなるのかは、わからないようだった。オバケ百科にも載っていない。それなら自分で調べるしか無い!と、小学生の時ぶりに、自由研究をしてみることにした。
図書館で、ほっぺた拾いオバケに関する文献をいくつか読んだ際に『なんでもオバケ相談窓口』という窓口の電話番号を見つけた。番号をメモして自宅に帰り、家の電話からかけてみると、女性が出た。
「はい。なんでもオバケ相談窓口です。オバケの種類をお願いします。」
マニュアルを読み上げるかのような淡々とした口調だった。ピザの宅配を受け付けるかのような、さらりとした対応。
「あ、えっと・・・ほっぺた拾いオバケについて調べたいんですけど・・・」
「ほっぺた拾いオバケですね。担当者に繋ぎますので、少々お待ち下さい。」
「はい。お願いします・・・」
保留音がしばらく流れた。居るのか。本当に。ほっぺた拾いオバケ担当者が。
「もしもし。お電話代わりました。ヨコタと申します。」
落ち着いた感じの、男性の声だった。
「あ、あの、ほっぺた拾いオバケについて調べているんですけれど・・・」
「ああ、はいはい。何を知りたいのでしょうか?」
「ほっぺた拾いオバケって、本当に居るんですかね?」
「ええ。居るからこそ、わたくしが担当しているんですけれど・・・」
「あ、そうですよね。えっと、彼らは拾ったほっぺをどうしているのかな、って疑問に思いまして・・・」
「ああ。それはですねぇ・・・我々にもまだわからなくてですね、研究中なのです。」
「そうなんですかぁ。どうしてもそのことが気になって仕方無いんですよ。あのぅ・・・もしお邪魔じゃなければ、僕もその研究に混ぜていただけないですかね?」
「え!?ご協力頂けるんですか!?今、うちの研究所、人手不足なんですよ。お手伝いいただけますと、大変助かります。」
そんなこんなで話はとんとん拍子に進み、“なんでもオバケ研究所”略して「オバケン」に行くことになった。ヨコタさんから教えてもらった住所をカーナビに入力し、出発した。オバケンは、山のほうにあるようだった。車を走らせ、山道を登っていく。やがて「ようこそ!オバケン!」というノボリが、道の両脇にズラリと並んでいる場所に着いた。近くまで来たらしい。
オバケンらしき建物を発見したので、駐車場に車を止めた。車を降りて、建物に近寄ってみる。オバケンは、普通の、家だった。家というか“別荘”のようなトンガリ屋根。ひょろ長い板に、「なんでもオバケ研究所」と書かれ、ドアの横にかかっている。インターホンを押してみると、インターホンからの応答が無いままに、ドアが開いた。
「キノシタさんですよね?どうもどうも。ヨコタです。」
ヨコタさんは、電話で話していた時は白衣の男を想像していたのだが、実際はGパンにTシャツというラフな格好のひょろりとした男性だった。
「キノシタです。よろしくお願いします・・・」
建物の中に入ると、廊下がまっすぐに伸びていて、左右にドアがいくつか。研究室もあれば、僕が電話をかけた相談窓口の対応をしている部屋もあり、その他にも、台所、茶の間、応接室、所長室などの他、カラオケルームだとか、ゲームセンターなどの娯楽施設まであるらしい。それらのプレートをちらちら見ながら、ずんずんと廊下の奥の方まで進んでいくヨコタさんに着いて行った。
歩いても歩いても、ずっと廊下が続いていた。各部屋のドアにかかっているプレートも、ヨコタ私物置場だとか、クリスマスの飾りだとか、ワイン貯蔵庫なんてのもあれば、床屋、パン屋、豆腐屋、おかしのまちおか、畳屋、動物病院、みどり電化チェーン、ママ・クリーニング小野寺よ、小僧寿し、シャディのサラダ館・・・と、まるで商店街のようなラインナップ。
「あの、ヨコタさん、これ、どこまで続くんですかッ!?」
両脇の不思議なラインナップのプレートたちに気を取られながら歩いていたせいで、ヨコタさんがかなり先の方を歩いていたので、早足で追いかけながら、質問してみた。ヨコタさんは、ピタリと足を止める。
「ああ、すみませんね。もくもくと歩いてしまって。」
「外から見た感じより、随分広いんですね。こんなに廊下が長いなんて。」
「初めて来た方は驚かれます。このオバケンの廊下は世界最長だと言われているんですよ。外から見た感じ、普通の一軒家に見えたかもしれませんが、実は山にトンネルを掘って、その中に研究所が広がっているんです。さっきのペンション風玄関口は飾りみたいなものです。」
「ええ!そうなんですかあ。そりゃすごいですねぇ。」
「もう少しで着きますから。」
再びヨコタさんはスタスタと歩きだす。
「・・・はい、ここです。僕の研究室。」
扉のプレートには「ヨコタ」とだけある。
「あまり片付いてないですけど、どうぞお入り下さい」
ヨコタさんに促され、部屋の中に入った。理科室みたいな感じだった。ひたすら物がいっぱいある理科室。大きなテーブルがいくつか。壁の戸棚には書類やら図鑑やらオバケの模型みたいなものとか、ぎっしり詰め込まれている。入って右手の壁には大きな黒板もある。
「どうぞおかけください。うちの名物“ビーカーコーヒー”飲みます?」
「ビーカーコーヒー?」
「インスタント珈琲をビーカーで飲むってだけなんですけどね。取っ手も無くて熱くて飲みにくいって大評判。飲みます?」
「あ、はい。じゃあ・・・。」
ヨコタさんは部屋の隅っこで何やらカタコトと道具を用意し、戻ってきた。
「お好きな温度で飲んでくださいね。」
僕の目の前に、三脚とアルコールランプが置かれ、その上に黒い液体が入ったビーカーが置かれた。
「ありがとうございます。」
「ほっぺた拾いオバケってのはね、割と最近発見されたオバケなんですよ。だからね、まだわからないことだらけなんです。ここに来る途中『小僧寿し』って書いたプレートが下がってる部屋がありましたでしょう?あれはね、超一流寿司職人の小僧がやってる店なんですよ。すんごく美味しいの。そこの大将の小僧は見た感じガキなんだけど、新鮮なネタ仕入れてるし、寿司握る腕もかなりなもんなんですよ。だからね、居るの。ほっぺた拾いオバケ。今晩、行きましょう。小僧寿し。」
「え!見られるんですか!ほっぺた拾いオバケ!」
「見えませんよ。でも、居るのはわかるんです。」
「どうやってわかるんですか?」
「耳を澄ますと、聞こえるんです。声とか、物音とか。」
「すごいですねえ!楽しみです!アチ!アチチ!!」
僕は、喜びの余り、ビーカーコーヒーで火傷した。
その日の夜、ヨコタさんと二人で『小僧寿し』というプレートが下げてある扉の部屋に入った。カウンター席のみで、椅子も5つぐらいしかない小さな寿司屋だった。ガラスケースに新鮮なネタが並び、カウンターの中に小僧が居た。思った以上に小僧だった。鼻が垂れている。
「へい!らっしゃい!何にしましょ!?」
「おすすめを5貫ぐらいずつ握ってもらおうかな。この人ね、今日から手伝いに来てくれたキノシタさん。」
「はじめまして・・・。」
「へい!よろしくね!キノシタさん!ぼく、まだ9歳だけど、小僧だけど、鼻垂れてるけど、寿司美味しいからね!食べてってね!」
小僧は鼻をかみ、寿司を握る準備を始めた。かなり手際がいい。
「まずはカツオね!へい一丁!」
小僧が握ってくれた寿司を食べてみた。ヨコタさんの言うとおりだ。小僧だと思って甘く見ちゃいけない。この寿司、本当に美味しい。ほっぺたが落ちそうだ。
「あ。」
僕はふと咀嚼を止めた。
「どうしました?美味しいでしょう?」
「ほっぺた、落ちちゃったかなと思って。オバケ、居ます?」
「しーーーー」
ヨコタさんは、口の前に人指し指をピンと立てた。
さっきまで鼻をすすっていた小僧も、ピタリと静かになった。
ヨコタさんの口が「い・ま・す」と動くのがわかった。
かなりかすかな音だが、キュッキュッと音がする。ガラス窓を拭いているような、こすれる音。 これがオバケが動く音か・・・?だとすれば、僕の近くに、オバケが居るようだ。
ヨコタさんは、音をたてないようにしながら、寿司を口に運んだ。目をつぶってじっくり味わっている。 すると、キュッキュッという音が増えた。
ヨコタさんが目を見開いて僕を見る。「やっぱり居ますね!」と言いたげだ。
僕はものすごくワクワクした。居るんだ、ここに。ほっぺた拾いオバケ!!
その日から、僕はヨコタさんの研究所に住み着いてお手伝いをしながら、二人で連日小僧寿しに通った。
毎晩毎晩、僕らは静かに寿司を食べた。 キュッキュッという音で、オバケがどのへんに居るか把握できるようになってきた頃、オバケを捕まえてみようという作戦に出てみることにした。文献によれば、まあるいらしい。手づかみをしようとすれば、手が滑るかもしれない。捕まえる為の網を用意してみた。
いつものように静かに寿司を食べる。耳を澄まして音を聞きながら、オバケが居そうな場所に、網をパタっと伏せてみた。しかし、網はぺしゃっとつぶれてしまう。何度か捕まえ損ねたものの、遂に手ごたえがあった。何も見えないが、網が動いているのだ。捕まえたようだ!
「やりましたね!キノシタさん!!」
「やったー!!」
僕らは大喜びで捕まえたオバケを網の上から掴んで、研究所に戻った。オバケは暴れることもなく、ただの柔らかいボールを持っているような感触だった。研究所に用意してあった犬用のケージにオバケを入れた。
「話しかけてみよう。怒ってるかな?」
ヨコタさんは少年のように目をキラキラさせながらケージを覗きこんでいた。 僕も横から覗き込んでみる。何も見えないけれど、居るんだ、きっと。
「こんにちはー」
「いや、こんばんはー!じゃないですか?」
「こんばんはー!」
「日本語通じるのかな。」
二人であれこれと話しかけてみた。しかし、何の反応もない。
「ヨコタさん、前にオバケの声が聞こえるとかって言ってませんでしたっけ。」
「ええ。稀に声が聞こえる時もあったんですよ。気のせいだったと言われればそうなのかもしれないけど、でも確かに聞こえたんです。」
捕まえてみたものの、ケージの中に入れてからはキュッキュッという物音もしなくなってしまったし、鳴き声みたいなのを期待したけど、何も聞こえなかった。僕らはビーカーコーヒーを啜りながら、何も入っていないように見えるケージをぼんやりと眺める。
「だしてー。ここからだしてー」
小さな小さな声が聞こえた。ヨコタさんと、目を見合わせる。
「だしてくださいー!ほっぺた返すからー!」
どうやら、ケージの中のオバケの声らしい。
「やっぱり居るんですね?オバケさん!」
ヨコタさんがケージの中に話しかける。
「なんなんですかー!?こんなところに閉じ込めてー!ばかー!お母さんに言いつけてやるー!」
「あらら。チビッコくんだったのかな。かわいそうなことしちゃいましたね、ヨコタさん。」
僕もケージに近寄ってみた。
「拾ったほっぺた、どうするのかなーって聞こうと思っただけなんですよ。ごめんね、ボク。」
ヨコタさんが、優しい声でオバケに話しかける。
「拾ったほっぺたは食べるんだよー。」
「え!?食べられるの???」
「うん。とっても美味しいんだ。軽く洗ってから、お日さまに当てて乾かして、おやつにするんだよ!お父さんは、ビールのおつまみに最高だね!って言うよ!たくさん拾って帰るとお母さんもすごく喜ぶんだ!本当にほっぺた落ちそうに美味しいんだよ!僕ら、ほっぺた無いから落っこちないんだ。だから拾いに来てるの。」
「そうなのかぁ。返せなんて言いませんから。大事に持って帰って下さいね。驚かせてごめんね、ありがとう。また来てください。」
ヨコタさんはそう言いながらケージの扉を開けた。
「どうもどうもー。ごちそうさまー。またねー。」
オバケはキュッキュッと音を立てながら帰って行った。(と、思う。なんせ見えないからわからない。)
「いやあ。スッキリしました。美味しいもの食べて落ちたほっぺたが美味しく食べられてたなんて、ねえ。」
僕は感動しながらヨコタさんにそう言った。
「キノシタさん!やりましたね!どこかの国でね、美味しいもの食べた時に“眉毛が抜けるほど美味しい!”ていうたとえをするんだそうです。ってことは、抜けた眉毛拾ってるオバケも居るんじゃないかと思ってるんです。次は、眉毛拾いオバケについて調べませんか!ほっぺたは美味しそうだけど、眉毛はねぇ!サスガに食べられないんじゃないですかねえ!」
ヨコタさんの目はますますキラキラと輝いた。
僕はしばらくこの研究所に居て、ヨコタさんとオバケの研究を続けることにした。
どうせ暇だし。
それに、寿司美味しいし。