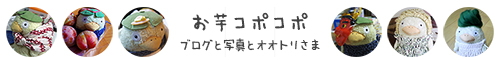割と最近のおはなしです。
あるところに、浦志真太郎(ウラシ・マタロウ)というおじいさんが居ました。
真太郎爺さんの日々の日課は、お散歩と喫茶店めぐり。今日も、お気に入りの喫茶店『キッサ・アクアリウム』へと向かいました。カタカナ表記がこじゃれています。 薄暗い店内には、幻想的な光を放つ水槽がたくさんあって、水族館のような喫茶店です。
「ここに来ると落ち着きますなぁ。いつものお願いね。」
お店のマスターの奥さんに、真太郎爺さんは声をかけました。すっかり顔なじみです。
「いつもありがとうございます。浦志さん。今日もごゆっくりしていって下さいね。」
真太郎爺さんは、いつも同じ席に座ります。お店のすみっこ、いちばん大きな水槽と壁に挟まれた、一人掛け用のソファとテーブル。コーヒーを飲みながら本を読んで過ごすおじいさんには、ちょうど良い広さというか狭さなのでした。
席に着くと、おじいさんは、本を読み始める前に、水槽の観察をします。小さな熱帯魚たちがスイスイと泳ぐ様子をしばし見つめ、ホっとひといきつくのでした。 そして、ふっかりとしたソファに身を沈めて、読みかけの本をカバンから取り出し、ぺらりぺらりと読み進めます。
やがて、一杯のコーヒーが運ばれてきました。真太郎爺さんの“いつもの”と言ったら、オリジナルブレンドコーヒーなのです。このお店のコーヒーは、注文してから豆を自家焙煎し、挽きたてを出してくれます。鼻をコーヒーカップに近づけなくても、なんとも良い香りが漂います。
コーヒーが運ばれてくると、おじいさんは一旦本を閉じ、ふたたび水槽を眺めながら、コーヒーをのみます。
ひとくち。ふたくち。
そしてまた、本の世界に戻ります。
コーヒーを飲み終えたころ、お店の奥で、この店のマスターと、その奥さんが何やら騒いでいる声がしました。おじいさん以外のお客さんも、その声に驚いてお店の奥をチラチラ見ています。
気になったおじいさんは、席を立ってカウンター越しにお店の奥を覗いてみました。
すると。
何やら奥のキッチンからもくもくと白い煙が上がっています。
「どうしたんですか!?火事ですか!?」
おじいさんはお店の奥に向かって呼びかけてみましたが、返事は無く、マスターと奥さんの悲鳴のような声が聞こえてくるだけでした。おじいさんは心配になり、お店とカウンターを仕切るパタパタした扉のところから、キッチンの方へと入って行きました。
キッチンは、もくもくした煙で満ちていました。
マスターと奥さんは、裏口から外に逃げ出したのかもしれません。煙であまりよく見えないのですが、ふたりの姿は既にないようでした。
火事かと思いましたが、火があがっている様子はありません。この煙は何だろう・・・と疑問に思ったおじいさんは、どこから煙が漂っているのか探してみました。
キッチンの片隅に水槽があり、その水槽からもくもくと煙があがっているようでした。何の煙かはわかりませんが、このままでは店内にまで煙が広がってしまうと思い、おじいさんは近くにあった段ボール箱をちぎり、水槽の上に乗せて蓋をしました。
煙はピタリと止まり、まっしろかった視界がだんだん開けてきました。換気扇があったので、紐を引いてスイッチを入れると、煙はみるみる吸い込まれていき、やがてキッチン全体が見渡せるようになりました。やはりマスターと奥さんの姿はありません。二人はどこへ行ってしまったのでしょう。
ひとまず煙は収まったのだし、客席に戻ろうとしたおじいさんは、ふと壁にかかった鏡に映る自分の姿を見て、とても驚きました。なんと、ものすごく若返っていたのです。さっきまで70代の老人だった自分が、どう見ても20代の若者の頃の姿なのです。
「どうしたことか、これは・・・。」
「やや、浦志さん、すみません。」
お店の裏口の扉からマスターが入ってきました。
「うちの家内がやらかしまして、すみません。」
「何ですか?あの煙は・・・。」
「若返りの煙です。」
「若返り?」
「あの水槽の中に若返りの煙を吐くカメを飼っているのです。」
「へえ。そんなカメが居るんですか。」
「ええ。毎日少しずつ煙を吐いてもらって、浴びるのがうちの家内の日課でしてね。しかしながら今日はカメにやるエサを間違えてしまいまして。尋常じゃない量の煙を吐くものですから、慌てて逃げてしまいました・・・
そうしたら浦志さん、あなた、こんな姿に・・・。」
どうやらおじいさんは、若返りの煙を吐くカメが吐き出した大量の煙を浴びたせいで、一気に若返ってしまったようなのでした。
「いやぁ・・・ビックリですが、うれしいです。これって効果はずっと続くんですかね?」
こんな異常事態でも、ポジティブシンキングなおじいさん(20代)なのでした。
「なんだかこんなことになってしまって申し訳ないんでね、うちの店の営業時間が終わったら、もう一度お店に来ていただけますか。お詫びをしたいので。」
帰りがけマスターにそう言われ、おじいさんは店を出ました。
若返っちゃったー!何して遊ぼうかなー!草野球!サッカー!鬼ごっこ!
見た目は20代まで若返ったおじいさんでしたが、ココロがすっかり少年に戻ってしまい、公園で少年達と泥だらけになって遊んでから帰りました。
家に帰ると、おばあさんが驚きのまなざしで見つめてきました。それはそうです。おじいさんがとびきり若返っているのですから。しかも泥だらけ。
「どうしたんですか、その姿は・・・。出会ったころを思い出しますよ」
「いやあ、ちょっとね、かくかくしかじかで。」
お婆さんが淹れてくれた熱いお茶を飲みながら、おじいさんは今日の出来事をおばあさんに話してあげました。
「まぁ、何日かで元の姿に戻ってしまうんじゃないかなあと思うんだ。だからそれまで毎日公園で草野球やサッカーなんかをやっちゃおうかなあ!」
お茶菓子もつまみながら、あれこれオシャベリをしていましたが、ふと、キッサ・アクアリウムのマスターに呼ばれていたことを思い出しました。
「ばあさんや、ちょっと出かけてくるからね。すぐ戻りますよ。晩御飯前には必ず。」
おじいさんはすたこらとキッサ・アクアリウムへと向かいました。
CLOSEの札がかかったドアを遠慮がちに押しあけると・・・マスターと奥さんがアロハシャツ姿で立っていて、おじいさんを出迎えてくれました。
「どうしたんですか、そのお姿は・・・」
「浦志さんに、お礼をしなければと思いまして。どうぞこちらに。」
奥さんに案内され、カウンターの奥のキッチンを抜け、裏口のドアを開けると、一台の車が止まっていました。
「浦志さん、後ろに乗って下さい。」
おじいさんの後ろからついてきたマスターが、運転席に乗り込みます。
奥さんが助手席に、おじいさんは後部座席に座りました。
「あれま。どちらへ行かれるのですかな。家内をうちに残してきてしまいましたよ。」
「それじゃあ、奥様をお迎えにゆきましょう。」
そう言ってマスターは、おじいさんの家へと車を走らせ、おばあさんを後部座席に座らせると、ぶんぶんと車を飛ばしてどこかに向かい始めました。
「あのぅ、どちらへ行かれるのでしょうか・・・?」
おばあさんは不安げな顔をして尋ねました。
すると、助手席の奥さんが
「海ですよ。海。」
と、とても楽しそうに言います。
「こんな時間から海に行っても真っ暗で何も見えないでしょう。」
おじいさんが言い返しますが
「やー、浦志さん、竜宮城は夜が綺麗なんですよ?。」
「え?竜宮城?」
「そうです。わたくしたち夫婦は竜宮城に住んでいるんですよ。毎朝竜宮城から『キッサ・アクアリウム』に出勤しているのです。」
とんでもないことを言い出すマスターに、困ってしまうおじいさんとおばあさんなのでした。
そんなこんなで、おじいさん(まだ20代のまま)とおばあさん(きらめく70代)を乗せた車は、海辺へと着きました。
「では、いきますよ。」
そう言ってマスターは更にアクセルを踏み込みました。
すでに時速100キロぐらいのスピードが出ていましたが、更に加速します。
そしてそのまま波打ち際を走り、海の中へと入っていくではありませんか!
「ちょ、ちょっとマスター!こんなの無理心中ですよ!」
「大丈夫ですよ、浦志さん。スピードを出しますからつかまって下さい。」
車はゴボゴボと音をたてながら海中へと進んでいきます。
夜の海はまっくらで、何も見えません。
車のライトがさす光の筋が2本見えるだけです。
後部座席では、おじいさんとおばあさんがヒシとお互いの腕を掴んで怖がっていました。
でも、窓やドアの隙間から水が入ってきてしまうこともないし、マスターと奥さんがニコニコ楽しそうにしているので、だんだん安心してきました。無理心中はなさそうです。
「ほら、見えてきましたよ、竜宮城。」
マスターの奥さんが、前方を指差して言いました。
車のライトの光の筋の向こうに、かすかに光っているものが見えました。
その光の方へ、車はどんどん近付いています。
何やら光り輝くきらびやかな建物が見えてきました。お城です。
「これが竜宮城・・・。」
確かに、暗い海の中で光るお城は、とてもとても美しいものでした。
おじいさんとおばあさんは驚きのまなざしでお城を見つめています。
やがて車は竜宮城の地下駐車場に入って行きました。
さきほどまで水中だったのですが、駐車場の中を走っているうちに水中ではなくなっていました。
車を降りても、普通に息が吸えます。
ここまで来るのは無事でも、お城の中も海水で満ちていたら、おじいさんとおばあさんはエラ呼吸ができないために死んでしまいますので、ほっと胸をなでおろしました。
「ご乗車お疲れ様でした。わたしたちの部屋へいらしてください。」
マスターと奥さんの住まいは、竜宮城のてっぺんの方にある一室でした。
3LDKぐらいある、マンションタイプの部屋でした。
4人でダイニングテーブルに座ると、魚っぽい顔立ちの使いの者がゾロゾロと部屋に入ってきて、ディナーの用意をし始めました。次々とごちそうが運ばれてきます。
「じゃあ、いただきましょうか。これは私たちからのお礼です。まずは、乾杯しましょう。」
マスターがそう言ってグラスを掲げます。
ワインで乾杯をして、ごちそうを食べました。
ものすごくおいしい中華料理でした。
ワインで乾杯で何故、中華料理なのかという疑問は、この非常事態において全く気にならないのでした。
料理を食べ終えると、リビングルームで魚っぽい顔立ちのダンサーたちが、機敏な動きでダンサブルにイス取りゲームに興じています。みんなでそれを見るのです。ダンスを見ているみたいでした。でも、椅子を取り合っているのです。おじいさんもおばあさんもとても楽しい気持ちになりました。おじいさんなんて、20代に若返っているままなのをいいことに、途中から混ざって一緒にダンサブルに椅子を取り合っていました。
この竜宮城では、外からのお客様をもてなす際、ワインで乾杯して中華料理を食べ、このダンサブル椅子取りゲームを一緒に見る、というのが最もポピュラーなもてなし方なのだそうです。この世には色んな文化があるものなのだな、とおじいさんは関心しました。
「じゃあ、そろそろ乙姫様にご紹介しましょうかね。」
そう言ってマスターはイスをずりずりしながらゆっくりと席を立ちました。
「そうですね、じゃあ、そろそろ行きましょうか。」
マスターの奥さんも、イスをずりずりしながら立ち上がります。
二人に連れられ、おじいさんとおばあさんは乙姫様の部屋へと向かいました。
50畳くらいありそうな大広間の真ん中に、乙姫様はぽつんとひとり静かに座っていました。
「乙姫様、お客様をお連れしました。」
「え。なに?ちょっと待って今ボス戦だから。セーブポイントまで待って。」
良く見ると、乙姫様はゲーム機のようなものを持っていました。PSだかDSだかTDLだかBLTだかっていうやつかもしれません。おじいさんとおばあさんの孫が持っているものに似ています。
数分間の沈黙(沈黙のBGMはゲーム機から流れる音楽です)ののち、ようやく乙姫様がゲーム機の電源を切って、話を聞く態勢になってくれました。
「乙姫様、我々が地上で飼っている亀のコウタローがですね、突然大量の煙を吐き出しまして、それをうっかり全身いっぱいに浴びてしまった、こちらの浦志さんがすっかり若返ってしまいまして・・・。」
「あらあら。それは大変ね。戻しましょう。」
さばさばっとしたキャリアウーマン的な印象の乙姫様です。
「いや、ちょっと待って下さい。私はこの若い姿をもう少し楽しみたい。」
「そうはいかないのよ、浦志さん。コウタローくんが吐く煙、確かに若返り効果があって、少量ずつ浴びてアンチエイジングに役立てている女性は数多く居りますけどね、大量に浴びてしまった場合は危険なのです。」
「危険・・・なのですか。」
「ええ。とても危険です。すぐに元に戻さないと、あなたは亀になってしまいます。」
「え!亀に!?」
「コウタローくんは亀の姿をしていますが、実は妖怪なのです。女性には優しいですが、男性にはあくどい事をします。なので、煙の成分が浦志さんの体全体に浸透してしまう前に、対処しなければなりません。」
というわけで、緊急手術のような手配が取られました。おじいさんは浴衣のようなものに着替えさせられ、魚っぽい顔の看護師さんたちがたくさん現れてはダンサブルに準備をしていました。さきほどのダンサーと同じ人たちのようです。多才な方々です。
大勢の看護師さんたちに取り囲まれたお爺さんは、突然体がふわっと浮かび上がったかと思うと、何度も何度も空中に放り投げられました。胴上げをされているようです。
「わー!なんですかこれはー!」
「ワーッショイ。ワーッショイ。」
お爺さんが叫んでも、胴上げは止まりません。
「あの、いったいこれは・・・」
おばあさんが乙姫様にかけよりました。
「大丈夫ですよ。奥様。見て下さい。ほら、年齢がどんどん・・・」
乙姫様にそう言われ、おばあさんは胴上げされているお爺さんを見てみました。なんということでしょう!さきほどまで20代だったおじいさんが、50代ぐらいになっているではありませんか!
「ワーッショイ。ワーッショイ。」
胴上げは続きます。やがて、おじいさんは実年齢の姿に戻りました。
地面に降ろしてもらったおじいさんは、足元がおぼつかず、よろよろとよろめいています。すかさずお婆さんがお爺さんを支えました。
「いやしかし、なぜに皆さん看護師のような格好だったんでしょうか。わたしゃ手術でもされるのかと思ってドキドキしていたのに突然胴上げなんかされて更にドキドキしましたよ。」
「恰好は雰囲気ですよ。雰囲気。竜宮城での治療は、みんな胴上げで行うんです。いちばん治りが早い。」
乙姫様は満面の笑みで答えました。どうも竜宮城のルールは良くわかりません。
その夜、おじいさんとおばあさんはマスターの家に宿泊し、翌朝『キッサ・アクアリウム』に出勤するマスターと奥さんに陸地まで送ってもらいました。
帰宅したおじいさんとおばあさんは、お茶を飲みながら竜宮城での出来事を思い出してオシャベリしました。夢だったのだろうか、とも思うのですが、お土産にもらってきた竜宮城名物「亀の姿の妖怪」が居ます。これが何よりの証拠です。リュウジというカッコイイ名前をつけ、かわいがりました。お婆さんはリュウジが吐きだす煙を少量ずつ浴び、若々しく過ごすことができたのでした。
数年後。
リュウジのエサは“パンの耳”だけを与えるように乙姫様に言われ、それを守り抜いてきたのですが・・・おばあさんが、ある夜、うっかり手を滑らせて自分がおやつに食べていたおせんべいをひとかけら、水槽の中に落としてしまったのです。すぐに気づいて拾えば良かったのですが、おばあさんは落としたことに気づいていませんでした。ばりんばりんとおせんべいを食べています。
気付かないまま、二人は就寝してしまいました。リュウジは、寝室で飼われていて、夜じゅうずっと煙をモクモクと吐き出し続けました。部屋中に煙が満ちていきますが、この煙は吸い込んでもけむたくない為、おじいさんもおばあさんも気づかずに朝までぐっすりでした。
翌朝目覚めると、煙をたっぷり浴びたおじいさんとおばあさんは、すっかり若返っていました。
「あらまあ、大変ですよ。おじいさん、起きて下さい。わたしたち、リュウジの煙を浴びて若返ってしまいましたよ。私はいいかもしれないけど、アナタは亀になってしまうかもしれません。胴上げしてもらいに竜宮城に行かないといけませんねえ。」
「あららら。こりゃ大変だわ。『キッサ・アクアリウム』に行ってマスターに相談しよう。」
割と悠長に考えていた二人でしたが、家の外に出てビックリ。リュウジが吐きだした煙は家の外にまで漏れ出ていて町中に蔓延していたのです。
そこへ、一人の若者が浦志家に駆け込んできました。誰かに似ています。
「浦志さーん!町中の人が若返ってしまいましたー。私は、『キッサ・アクアリウム』のマスターです!」
そう名乗った10代のマスターは、ピシっと背筋を正しました。
「えええ!?マスター!?若ッ!大変なことになっちゃいましたね。すみません。うちのリュウジがパンの耳以外のものを食べてしまったみたいで・・・一晩中、煙が出続けていたようなのです。町中の人を胴上げしてもらうわけにもいかない・・・何とかなりませんか。」
「そう思ったんですけどね。さきほど乙姫様に電話で相談したところ、『みんなが若返ったなら、それでいいじゃない』と言うんですよね。」
「え!?若返ったままで居て大丈夫なんですか!?みんな亀になっちゃったりしませんか!?」
「そうなったらそれはその時に考えましょうか。町中のみんなが亀になったら、みんなで竜宮城のまわりに村でも作りましょうよ!亀の村!わっはっは!」
竜宮城に住む人々は、楽観的なのでありました。
じゃあ、まあいっか。というわけで、めでたしめでたし。